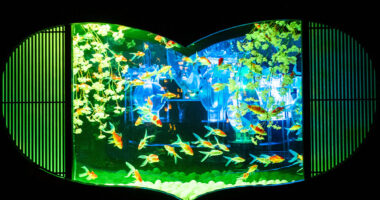日本を訪れるなら、ぜひ味わっていただきたいのが、古くから人々に親しまれてきた日本の伝統的な酒です。
地域や風土に根ざしたさまざまな種類のアルコールが存在し、全国的に流通している銘柄もあれば、その地域でしか出会えないレアなものも存在します。
日本酒をはじめ焼酎、泡盛など、それぞれ原料や製法が異なり、味わいも個性豊か。アルコール度数も幅広く、10%前後のものから、30%を超えるしっかりとした風味の酒まで、バリエーションも多彩です。
日本酒

※日本酒のイメージ
日本ならではのアルコールと聞いて、日本酒をまず思い浮かべる人も多いでしょう。
米と水、そして麹の力でつくられる日本酒は、古くから人々の暮らしに寄り添ってきた日本の伝統的な酒です。
日本全国で広く親しまれており、飲食店はもちろん、コンビニやスーパーマーケットでも購入でき、手軽に楽しめます。
しかし、日本酒には地域ごとに異なる個性があり、中にはその酒蔵がある周辺地域でしか出会えない限定銘柄も。
そんな『地酒』と呼ばれる、地域に根差した日本酒を探して旅するのも、粋な楽しみ方です。
また、日本酒は四季の移ろいとともに変化する酒でもあります。冬には、収穫したての新米で仕込まれた『新酒』が登場し、フレッシュでさわやかな味わいを楽しめます。
夏には、すっきりとしたのどごしの『夏酒』が人気で、キリッと冷やして飲むのがおすすめ。季節を五感で味わえるのが日本酒の大きな魅力です。

※日本酒の熱燗のイメージ
アルコール度数:13〜16%前後
ほどよいアルコール度数で、食中酒としても楽しみやすく、和食だけでなく洋食とも好相性。刺身や寿司、はては揚げ物など、ジャンルを問いません。
ただし飲みすぎにはご注意を。日本酒を楽しむ合間に水も一緒に飲むと、過度に酔いにくくなります。
日本酒のおすすめの飲み方
日本酒は温度によって味わいが大きく変わります。冷やして飲むとすっきりとした後味で、暑い季節には食中酒としても楽しめます。
常温ではまろやかな口当たりで、味わいのバランスが絶妙です。
冬の寒い時期には熱燗がおすすめで、温めることで米の甘みやうまみが膨らみ、身体も温まります。
焼酎

※焼酎のイメージ
日本酒と並んで、日本を代表する伝統的なアルコールが焼酎です。
蒸留酒である焼酎は、アルコール度数がやや高めで、すっきりとした後味。日本の南部、特に九州地方で広く親しまれ、日常的に飲まれています。
焼酎の魅力はなんといっても、原料によって風味が大きく変わること。
サツマイモ、麦、米、黒糖、そば、クリなど、さまざまな素材が使われ、それぞれに香りや味わいの個性があります。
芋焼酎を例にあげると、香ばしくふくよかな香り。麦焼酎は、クセが少ないため後味が軽やかで飲みやすく、焼酎初心者にもおすすめです。
さらに、奄美諸島でしか製造が許されていない黒糖焼酎もあり、こちらはほんのり甘みのあるやさしい味わいが楽しめます。
焼酎は、飲み方のバリエーションが豊富なのも嬉しいポイント。ロックや水割り、お湯割り、炭酸割りなど、好みや季節に合わせて楽しめます。

※焼酎のロックのイメージ
特に寒い季節のお湯割りは、焼酎の香りをふわっと立たせてくれるので、心も身体も温まります。
近年では香り高いプレミアム焼酎や、海外輸出向けのモダンなデザインのボトルも増えており、外国人観光客からの注目も高まっています。
アルコール度数:25〜30%前後
一部の焼酎は20%台前半ですが、総じて日本酒よりも少し強めのアルコール度数。麦焼酎はチューハイやハイボールにも使われます。
炭酸割りや水割りの場合、意外とスイスイ飲めてしまうため、飲みすぎにはご注意ください。
焼酎のおすすめの飲み方
焼酎は原材料によって適した飲み方が異なります。
米焼酎はまろやかで上品な香りが特徴なので、ロックや水割りがおすすめです。
麦焼酎は香ばしく軽快な味わいで、炭酸割りで楽しむのも人気。芋焼酎はコクと甘みが強いため、ロックやお湯割りでじっくり味わうのが定番です。
初心者の場合は、どの焼酎もまずは水割りもしくは炭酸割りから試してみるといいでしょう。
泡盛

※『銀座わしたショップ 本店』で取り扱う泡盛の一例
沖縄を訪れたら、ぜひ味わっていただきたいのが、泡盛。日本最南端の島で育まれてきたこの酒は、日本最古の蒸留酒ともいわれています。
タイ米と黒麹菌を主原料に仕込み、しっかりとしたコクと香り、そして南国らしい力強さが特徴です。
フレッシュな泡盛は、ややドライで個性的な香りが印象的。ロックや水割りはもちろん、ソーダ割りにしてすっきりと楽しむのもおすすめです。
アルコール度数は25〜30%前後とやや高めですが、飲み方次第でぐっと飲みやすくなります。

※古酒のイメージ
そして、泡盛の大きな魅力の1つが古酒(クース)の存在です。
泡盛は寝かせるほどに味がまろやかになり、香りも落ち着いていきます。
3年以上熟成されたものを古酒と呼び、長いもので10年、20年と時を重ねた泡盛も。
古酒はアルコール特有の味の角が取れ、なめらかな口当たりのため、泡盛初心者にもおすすめです。
なお、アルコール度数は古酒のほうがやや高めで、30〜40%ほど。熟成年数が長いほど、香りとコクのバランスも深くなっていきます。
アルコール度数:(泡盛)25〜30%前後(古酒)30~40%前後
一般的な泡盛は、日本酒やワインよりやや高めですが、水割りや炭酸割りにすることで、飲みやすく楽しむことができます。
古酒はそれよりさらに高く、30~40%前後。ストレートやロックでじっくりと味わうのが好まれます。
泡盛のおすすめの飲み方
泡盛は度数が高く、その風味も含めて楽しむためにも、ロックで飲むのが基本です。
ただし、さわやかな後味を楽しみたい場合は炭酸割りもよく、こちらは暑い季節にぴったり。
古酒はまろやかで深い味わいが特徴なので、ストレートやロックでじっくりと。香りを楽しみながら飲むのがおすすめです。
ハブ酒

※ハブ酒のイメージ
泡盛や古酒の深い味わいを楽しんだ後は、沖縄ならではのもう1つのユニークなアルコールである、ハブ酒にも注目してください。
ハブ酒は、沖縄の伝統文化と密接に結びついており、泡盛にハブという毒ヘビを漬け込んで作られています。
アルコール度数が高い泡盛がベースのため、パンチのきいた味わいです。
独特の風味とハブから抽出された成分が混ざり合い、薬膳酒のような効能も期待されることから、体力増強や健康維持のために飲まれてきた歴史があります。
ハブ酒は特別なお土産や健康を願う縁起物としての意味合いもあり、沖縄以外の一般の飲食店ではあまり流通していないレアなアルコールです。
アルコール度数:30~40%
泡盛がベースであるため、アルコール度数はかなり高く、少量ずつ味わうのがおすすめです。
体力増強や健康を願うお守り的な意味合いもあるため、じっくりとその味と文化を楽しんでみてください。
ハブ種のおすすめの飲み方
ハブ酒は強いアルコール度数を持つため、ショットで少量ずつ味わいます。
氷を入れたロックのスタイルでも飲まれますが、強さを和らげたい場合は炭酸割りやソーダ割りにする方法も。
薬膳酒としての側面もあるため、じっくり体調に合わせて楽しむのがよいでしょう。
梅酒(果実酒)

※梅酒のイメージ
梅酒は、日本の伝統的な果実酒の代表格として、老若男女に親しまれている甘くて飲みやすいアルコールです。
まだ熟していない、皮が青い状態のウメの実を氷砂糖や焼酎、または日本酒に漬け込み、数か月から数年かけてじっくりと味を引き出します。
自宅で手作りされることも多く、初夏の風物詩として愛されてきました。
梅酒の魅力は、その甘酸っぱさとまろやかな口当たり。食前酒やデザート酒としてもぴったりで、食事のシーンをやさしく彩ってくれます。
梅酒のほかにも、果実酒の種類は実に多彩。代表的なものには、柚子やアンズを使った果実酒があり、それぞれの果物の香りや味わいを生かしたバリエーション豊かなラインナップが魅力です。
これらの果実酒は、地域ごとの特産品を活かした限定品も多く、お土産としても人気があります。

※果実酒のイメージ
アルコール度数:10〜15%程度
梅酒をはじめとした果実酒は、甘みが強く、アルコールのクセが抑えられているため、初心者でも飲みやすく感じられるでしょう。
ロックやソーダ割りでさわやかに、またはお湯割りで温かく味わうなど、季節や気分に合わせてさまざまな飲み方が可能です。
梅酒(果実酒)のおすすめの飲み方
梅酒や果実酒は甘くて飲みやすいので、まずはロックで香りと味わいを楽しんでみてください。
炭酸割りにするとぐっと飲みやすくなり、夏場にもぴったりの飲み方です。
寒い季節にはお湯割りもおすすめで、身体が温まるのと同時に、原材料の果実ならではの甘みが引き立ちます。
多彩な伝統酒は、旅先でその土地ならではの味との出会いや、文化や歴史にも触れることができるきっかけになります。
ぜひ自分にぴったりの1杯を見つけて、特別な旅の思い出にしてみてください。